相続がきっかけで、仲の良かった兄弟姉妹の関係が壊れてしまう──
そんなケースを、これまで数多く見てきました。
「うちは仲がいいから大丈夫」
「兄弟で揉めるなんて他人事」
そう思っているご家庭ほど、事前の備えがないことでトラブルに発展することが少なくありません。
今回は、高槻市で民事業務を専門に扱う行政書士の視点から、
“兄弟の仲を壊さないための相続対策”と、“揉めない家族に共通する特徴”をお伝えします。
1. なぜ兄弟で相続トラブルが起こるのか?
相続の争いは、財産の多い家だけに起こるものではありません。
実際には、数百万円〜数千万円の規模でも感情的なもつれが原因でトラブルに発展します。
主な原因は次の通りです。
- 親が「誰に何をどう渡すか」を明確にしていなかった
- 介護や同居など“貢献度”に差がある
- 生前贈与や援助に偏りがあり、不公平感が生まれる
- 不動産(特に実家)が分けにくい財産である
特に「実家の名義をどうするか」「誰が住み続けるか」は、多くの兄弟間トラブルの火種になります。
2. “揉めない家族”がしている3つのこと
これまでの相談対応の中で、円満に相続を迎えた家族には共通点がありました。
それは次の3つです。
① 親が早い段階で意思を示している
元気なうちに「自分の財産をどうしたいか」を家族に話している方は、
相続発生後に兄弟が迷うことがありません。
遺言書や財産メモを残しておくことで、
家族が「親の意思」を尊重しやすくなり、トラブルの芽を摘むことができます。
② 兄弟で“情報の共有”ができている
相続で揉める家庭の多くは、一部の兄弟だけが情報を持っているケースです。
たとえば、「通帳や不動産の情報を知らない」「介護費用の負担状況を把握していない」など。
“揉めない家族”は、
- 親の財産・介護・生活状況をオープンに共有
- 定期的に話し合う場を持っている
という特徴があります。
特に介護を担っている兄弟の努力をきちんと理解し合うことが大切です。
③ 感情とお金を分けて考えられる
相続では、「公平」と「平等」は必ずしも一致しません。
介護や金銭的支援など、“目に見えない貢献”があるからです。
揉めない家族は、
「兄が介護をしてくれたから、少し多めに受け取っていい」
「お金よりも感謝を形にしたい」
といったように、感情を整理し、理性的に判断できています。
3. トラブルを防ぐためにできる具体的な対策
● 遺言書の作成
親が元気なうちに公正証書遺言を作成するのが最も確実です。
「誰が何を継ぐか」を明記しておくことで、兄弟間の不満を防ぎます。
● 家族会議を開く
お盆や正月など、全員が集まるタイミングで「将来の話」をすることをおすすめします。
行政書士など第三者を交えると、感情的にならずに整理がしやすくなります。
● 財産と介護の見える化
「どんな財産があるか」「介護費用を誰がどれだけ負担しているか」を一覧にまとめると、
公平な相続を検討しやすくなります。
4. 高槻市での相談事例
高槻市内でも、兄弟間の相続トラブルを防ぐために、早めにご相談に来られる方が増えています。
あるご家庭では、
- 長男が同居・介護を担当
- 次男が遠方に住み、財産内容を知らなかった
という状況でしたが、遺言書と財産管理表を作成し、
兄弟で合意書を交わしたことで、相続後も良好な関係を維持できました。
「親が元気なうちの一歩」が、将来の兄弟関係を守ります。
5. まとめ:相続は“財産分け”ではなく“家族の調整”
相続は単なる財産の分け方ではなく、家族の関係をどう保つかというテーマです。
兄弟の仲を壊さないためには、
「話す」「残す」「共有する」――この3つを早めに実行することが鍵となります。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です
ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

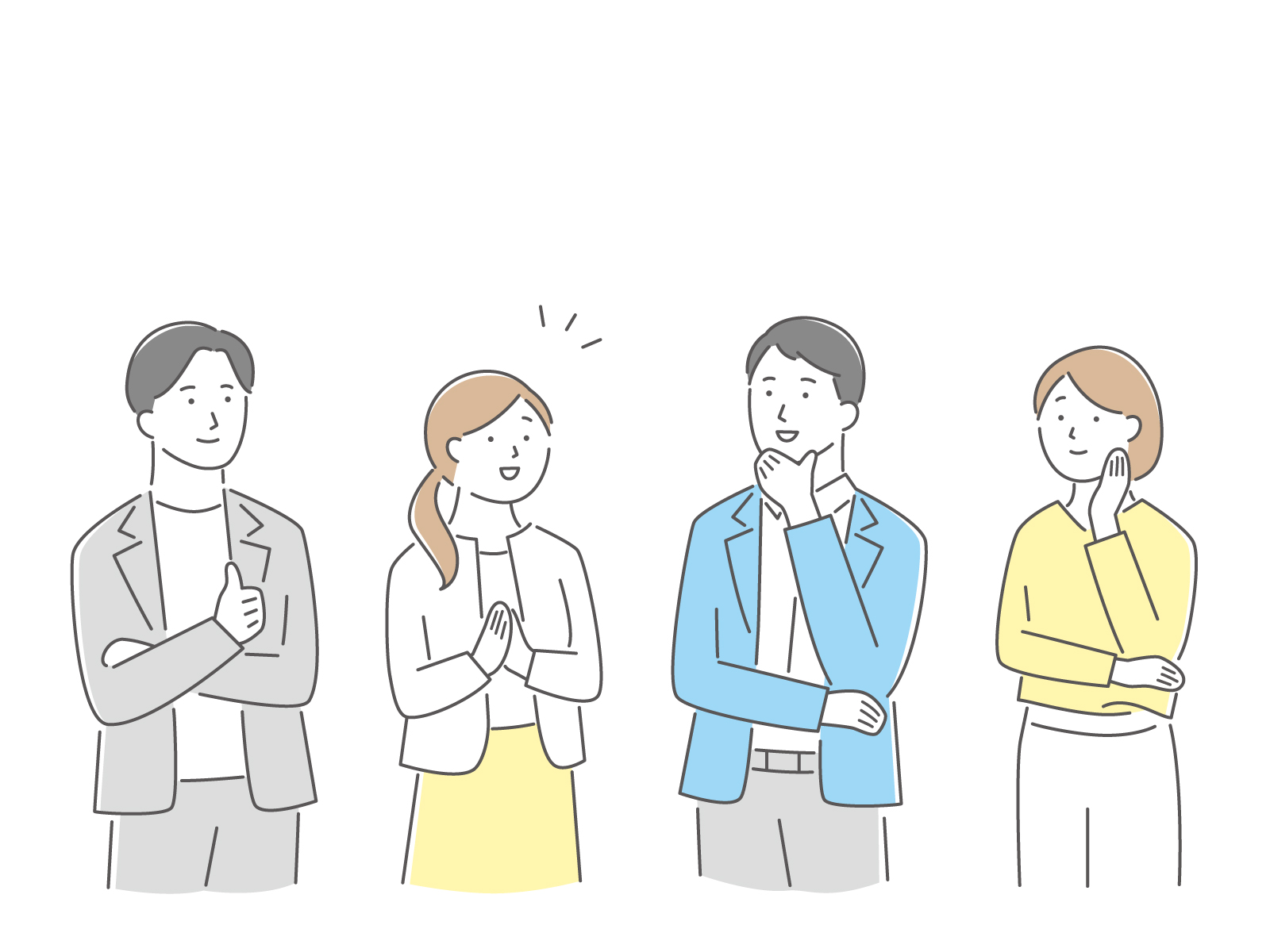
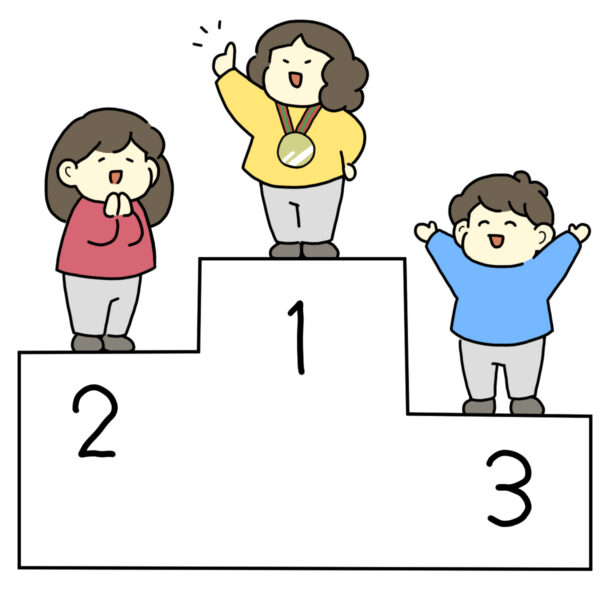

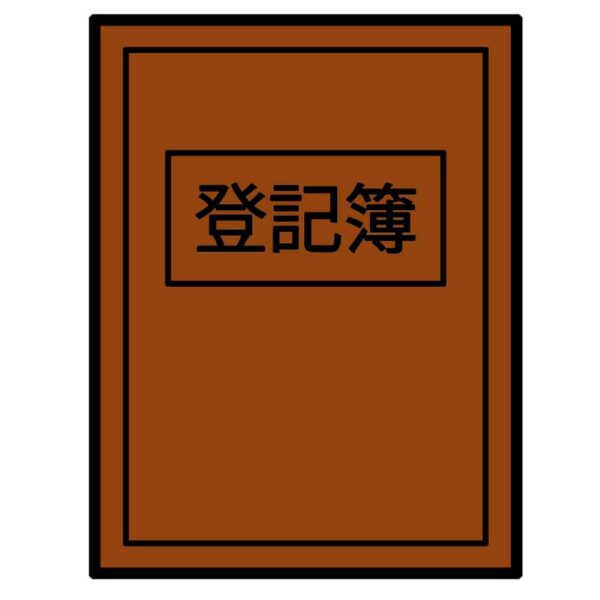



コメント