親の介護が現実的な課題となる年代になると、「介護」と「相続」の両方を意識する必要が出てきます。
介護と相続は切り離せないテーマであり、どちらか一方だけを考えると後々トラブルの原因となることもあります。
今回は、高槻市で民事業務を専門とする行政書士の立場から、「親の介護と相続対策を同時に考える方法」について解説します。
1. 介護と相続は“同じタイミング”で考えるべき理由
多くの方は「介護が落ち着いてから相続を…」と考えがちですが、実際には介護の最中に相続を見据えた準備を進めることが大切です。
- 介護に関する費用や不動産の管理方法を明確にしておくことで、将来のトラブルを防げる
- 親の意思確認を早めに行うことで、後の「遺言書」作成がスムーズになる
- 兄弟姉妹間の不公平感を減らし、相続発生後の争いを予防できる
つまり、「介護」と「相続」は時間を空けず、並行して考えるのが理想です。
2. 介護をきっかけに整理しておくべきこと
親の介護が始まった時点で、以下の点を家族で話し合っておきましょう。
● 財産と収支の見える化
親名義の銀行口座、不動産、年金、介護費用などを整理します。
家族の誰が管理するのかを明確にしておくと、後々の誤解を防げます。
● 介護方針と役割分担
「誰が介護を中心に担うのか」「施設入所の判断はどうするのか」を決めておくことが重要です。
この話し合いが、後の寄与分(相続時の貢献度評価)にも関係します。
● 親の意思確認
「どのような介護を望むか」「自宅をどうしたいか」「財産の分け方の希望」など、本人の意向を尊重しながら確認します。
3. 同時に進めたい3つの法的対策
介護と相続を同時に考える際には、次の3つの法的手続きが特に効果的です。
① 任意後見契約
認知症などで判断能力が低下する前に、「信頼できる人に財産管理を任せる契約」です。
将来の不安を軽減し、介護費用の支出や手続きをスムーズに進められます。
② 財産管理契約
親がまだ元気なうちに、銀行手続きや支払いを代理してもらえるようにする契約です。
介護が長期化した場合に備え、生活資金の管理を明確にできます。
③ 遺言書の作成
介護を担った子どもが報われるようにするには、親の意思を明確に残すことが大切です。
公正証書遺言を作成しておくと、後の争いを防ぎやすくなります。
4. 家族で話し合うタイミングとコツ
家族で話す際には、次の点を意識するとスムーズです。
- 感情的にならず、「親の希望を中心に」話を進める
- 兄弟姉妹の全員が揃う機会(お盆・正月など)を活用する
- 第三者を交えて冷静に整理する
特に、高齢の親御さんが元気なうちに話しておくことで、後悔のない形を作れます。
5. 高槻市でのサポート事例
高槻市でも、親の介護が始まった段階で相続対策を進めるご相談が増えています。
たとえば――
- 認知症になる前に任意後見契約と遺言書をセットで作成
- 自宅をリフォームして介護対応にする際に、不動産の相続方針を確定
- 介護している子が生活資金を負担している場合の公平な分配方法を設計
こうした事例では、第三者が家族全体の調整役としてサポートすることで、円満な介護と相続を両立できます。
まとめ
親の介護と相続対策は、どちらも「家族の未来」に関わる大切な問題です。
タイミングを逃さず、信頼できる専門家と一緒に考えることで、家族全員が安心して向き合える環境をつくれます。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です
ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。


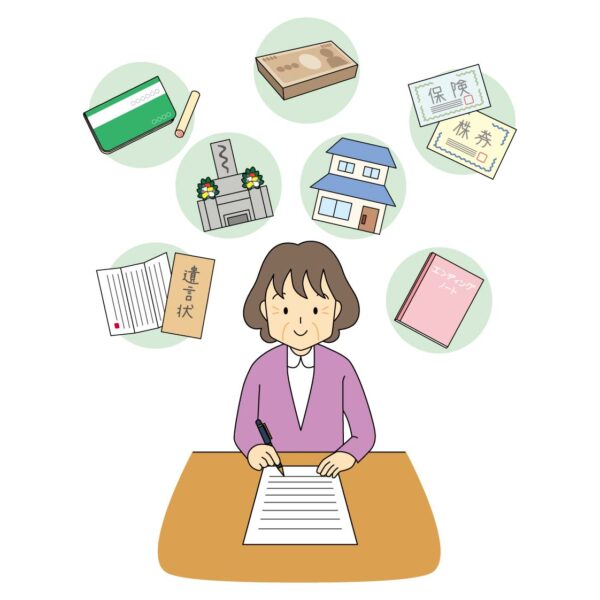





コメント