はじめに
相続手続きを進める際に、ほとんどの方が一度は耳にする「登記簿」。
しかし、「どんな情報が書かれているの?」「どこで入手できるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、高槻市で民事業務を専門とする行政書士が、相続で必要となる登記簿についてわかりやすく解説します。
登記簿とは?
登記簿とは、不動産(土地や建物)に関する権利関係を公的に記録した帳簿のことです。
法務局が管理しており、不動産の所在地・所有者・抵当権などの情報が記載されています。
現在は紙の登記簿ではなく、「登記簿謄本(登記事項証明書)」という形で発行されます。
相続で登記簿が必要となる理由
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、相続人に名義変更(相続登記)する必要があります。
その際に、
- 誰の名義になっているのか
- どのような不動産があるのか
- 抵当権や地上権などの権利関係がどうなっているか
を確認するために、登記簿が必要になります。
登記簿は、相続財産の全体像を把握するうえで欠かせない書類です。
登記簿の種類と構成
登記簿は、主に以下の3つの部分で構成されています。
- 表題部(ひょうだいぶ)
不動産の所在・地目・地積・構造などの基本情報が記載されています。
例:「高槻市○○町1丁目」「宅地」「200平方メートル」など。 - 権利部(甲区)
所有者の氏名や住所、所有権移転の原因(売買・相続など)が記載されています。
相続登記では、この「甲区」の名義変更が行われます。 - 権利部(乙区)
抵当権や賃借権など、所有者以外の権利が設定されている場合に記載されます。
登記簿の取得方法
登記簿(登記事項証明書)は、以下の方法で入手できます。
- 法務局の窓口で申請
全国どこの法務局でも発行可能です。 - オンライン申請(登記情報提供サービス)
インターネットで登記情報を閲覧・取得することができます(ただし、閲覧用データは正式証明書ではありません)。 - 郵送請求
最寄りの法務局に郵送で申請も可能です。
取得手数料は窓口で600円、オンライン請求なら500円程度です(2025年現在)。
相続登記の義務化と注意点
2024年4月から、相続登記の義務化が始まりました。
不動産を相続した場合、相続開始(被相続人が亡くなった日)から3年以内に登記申請を行う必要があります。
正当な理由なく登記を怠ると、過料(最大10万円)の対象になることもあります。
そのため、登記簿を早めに取得し、対象となる不動産の確認を行うことが重要です。
行政書士に相談するメリット
登記そのものは司法書士の専門分野ですが、
行政書士は相続人の確定・遺産分割協議書の作成・戸籍調査など、登記前の重要な手続をサポートできます。
- 相続財産の全体把握
- 相続人の調査
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
といった手続きを行政書士に依頼すれば、登記申請の準備をスムーズに進めることができます。
また、司法書士と連携しスムーズな相続手続きが可能です。
まとめ
登記簿は、相続手続きの出発点ともいえる大切な書類です。
名義変更や不動産の確認を行うためには、正確な登記簿情報が欠かせません。
高槻市で相続に関するご相談や登記準備をお考えの方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
専門的な知識で、相続手続きを安心・確実にサポートいたします。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です
ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

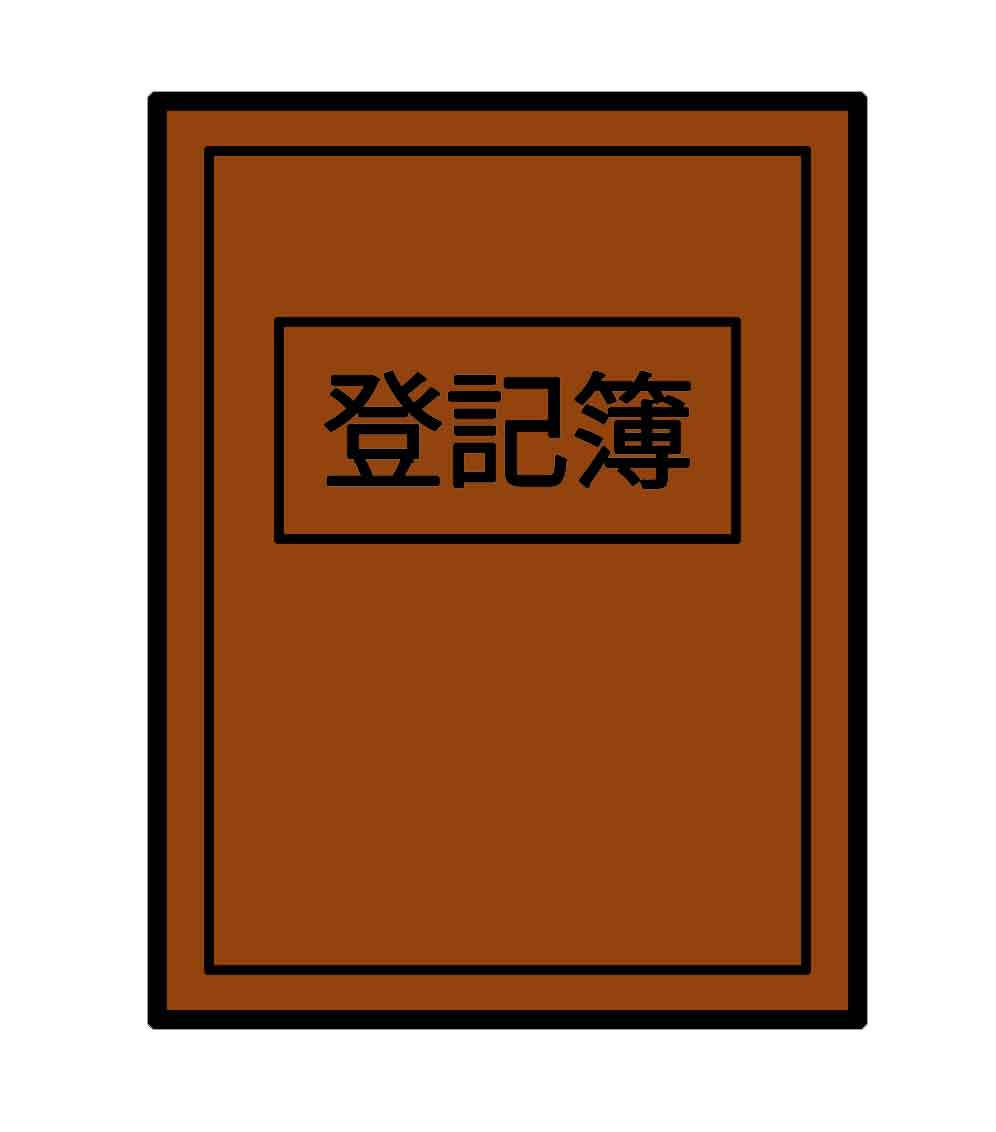

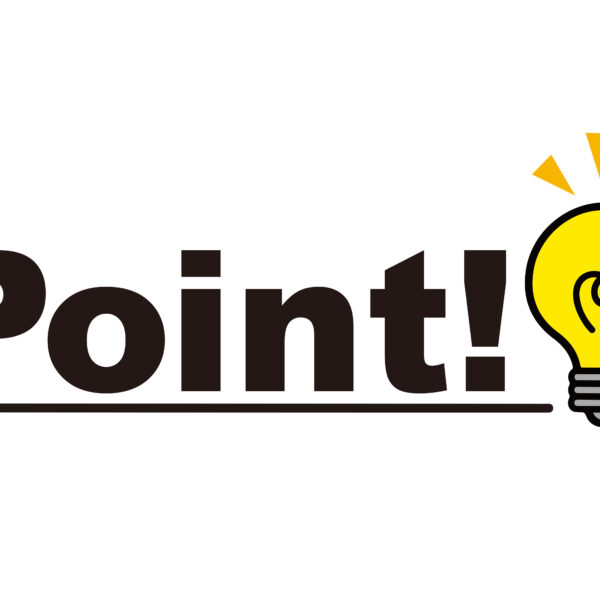




コメント