遺贈とはなにか
「遺贈(いぞう)」とは、遺言書によって、自分の財産を相続人以外の人や団体に贈与することをいいます。
通常、財産は民法で定められた「法定相続人」に引き継がれます。例えば、配偶者や子どもが代表的な相続人です。しかし、遺贈を活用すれば、相続人以外の人へ財産を渡すことができます。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
- 長年お世話になった友人に感謝の気持ちを形にしたい
- 縁の深いお寺や神社、社会福祉法人、NPO法人に寄付をしたい
- 血縁関係はないが一緒に暮らしてきたパートナーに財産を残したい
このように「法律上の相続人ではない人や団体に財産を承継できる」点が、遺贈の大きな特徴です。
遺贈の種類
遺贈には主に次の2つの種類があります。
1. 包括遺贈
財産全体のうち一定の割合を指定して遺贈する方法です。
例:「私の財産の2分の1を友人のAさんに遺贈する」
包括遺贈を受けた人は、相続人とほぼ同じ権利・義務を持つことになり、相続人と同様に借金などの負債も引き継ぐ可能性があります。
2. 特定遺贈
特定の財産を指定して遺贈する方法です。
例:「自宅の土地をBさんに遺贈する」「預貯金のうち○○銀行の口座をCさんに遺贈する」
特定遺贈は、対象となる財産が明確なため、実務上利用されることが多い方法です。
遺贈と相続の違い
相続と遺贈は似ていますが、法律上の性質は異なります。
- 相続 … 配偶者や子どもなど、法律で定められた相続人が財産を承継すること
- 遺贈 … 遺言に基づいて、相続人以外の人や団体に財産を承継することができる
相続人がいない場合でも、遺贈を活用すれば財産を希望する相手に残せます。一方で、遺贈を受ける人には「承認」または「放棄」の選択権があり、必ずしも受け取らなければならないわけではありません。
遺贈の手続きと注意点
遺贈を実行するには、遺言書が必要です。遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、実務的には公正証書遺言が最も安心です。公証人が関与するため、形式の不備によって無効となるリスクを防げます。
ただし、遺贈には次のような注意点があります。
1. 遺留分の問題
相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。遺贈によってこれを侵害すると、相続人から「遺留分侵害額請求」が行われる可能性があります。
たとえば、「全財産を友人に遺贈する」としても、配偶者や子どもなどの相続人がいれば、その権利を侵害することになります。
2. 登記や手続きの複雑さ
不動産を遺贈する場合、登記の名義変更が必要です。相続の場合と手続きが異なる部分があり、書類の準備も複雑になるため、専門家(司法書士、弁護士)に依頼するケースが一般的です。
3. 税金への影響
遺贈を受けた人には、相続税が課税される可能性があります。相続人ではない人が遺贈を受ける場合、税率が高くなることもあるため注意が必要です。例えば、相続人でない知人が遺贈を受けると、最大で相続税の55%が課される場合もあります。
高槻市で遺贈を検討される方へ
遺贈は「自分の意思を尊重し、大切な人や団体に思いを託すこと」ができる有効な制度です。
しかし、法律的なルールや税金の問題を十分に理解しておかなければ、遺贈を巡って相続人とのトラブルに発展してしまうこともあります。
高槻市で民事業務を取り扱う行政書士として、私は次のようなサポートを行っています。
- 公正証書遺言の作成サポート
- 遺贈に関する法的アドバイス
- 相続人や受遺者との調整方法のご提案
- 登記や税務手続きの専門家との連携
「遺贈を考えているけれど、遺言はどう書けばよいのか不安…」
「相続人以外に財産を渡したいが、トラブルにならないか心配…」
このような悩みがある方は、ぜひ早めにご相談ください。専門家に相談することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
✅ 遺贈は、人生の最後に「想いを形にする手段」としてとても大切です。高槻市で遺贈や遺言書の作成をお考えの方は、お気軽に行政書士へご相談ください。
事務所名:乾行政書士事務所
代表者:乾 公憲
住所:大阪府高槻市上牧北駅前町4番50号
📌 対応エリア:茨木市、高槻市、枚方市、交野市、吹田市、摂津市、箕面市、寝屋川市
📞 お問い合わせ:072-691-5370
📩 メールでのご相談も受付中です
ごあいさつ
私は、障がい福祉サービスに特化した行政書士として、これまで多くの事業者様の立ち上げ・運営支援に携わってまいりました。高齢者や障がいのある方、そのご家族が安心して暮らせる地域づくりを支援することを使命とし、制度理解から各種申請、運営の課題まで、丁寧かつ実務的にサポートしております。
このたび、より幅広いニーズにお応えするため、遺言・相続・死後事務委任契約・成年後見制度の利用支援など、民事法務の取り扱いも開始いたしました。とくに、福祉の現場に近い立場で業務を行ってきた強みを活かし、ご本人の思いやご家族の不安に寄り添った法的支援を心がけております。
障がい福祉と民事業務の両面から、「支援が必要な方々の権利と暮らしを守る」ことを目指し、地域に根ざした専門家として真摯に取り組んでまいります。どうぞお気軽にご相談ください。


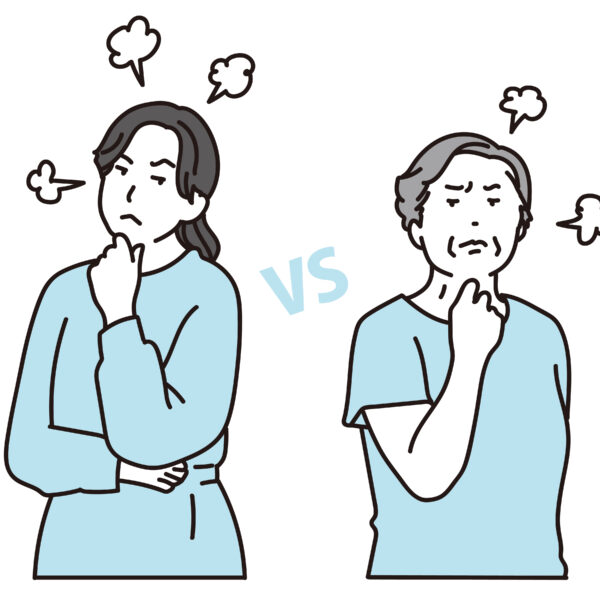
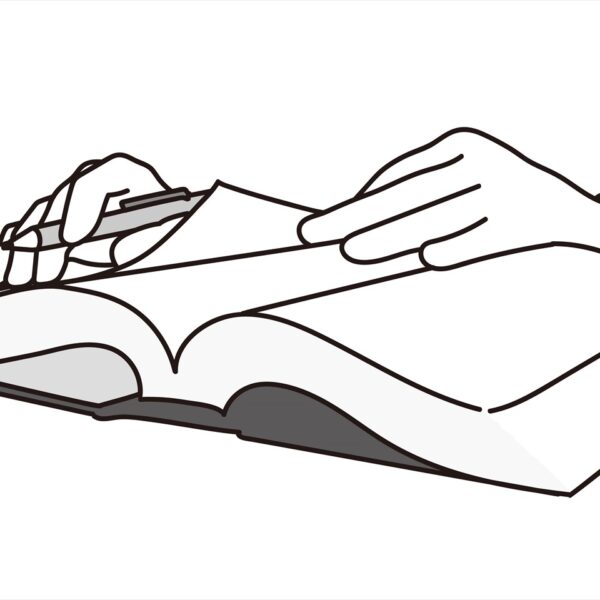




コメント